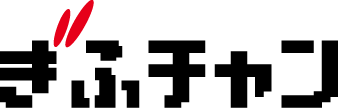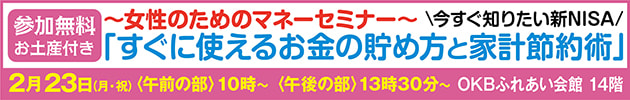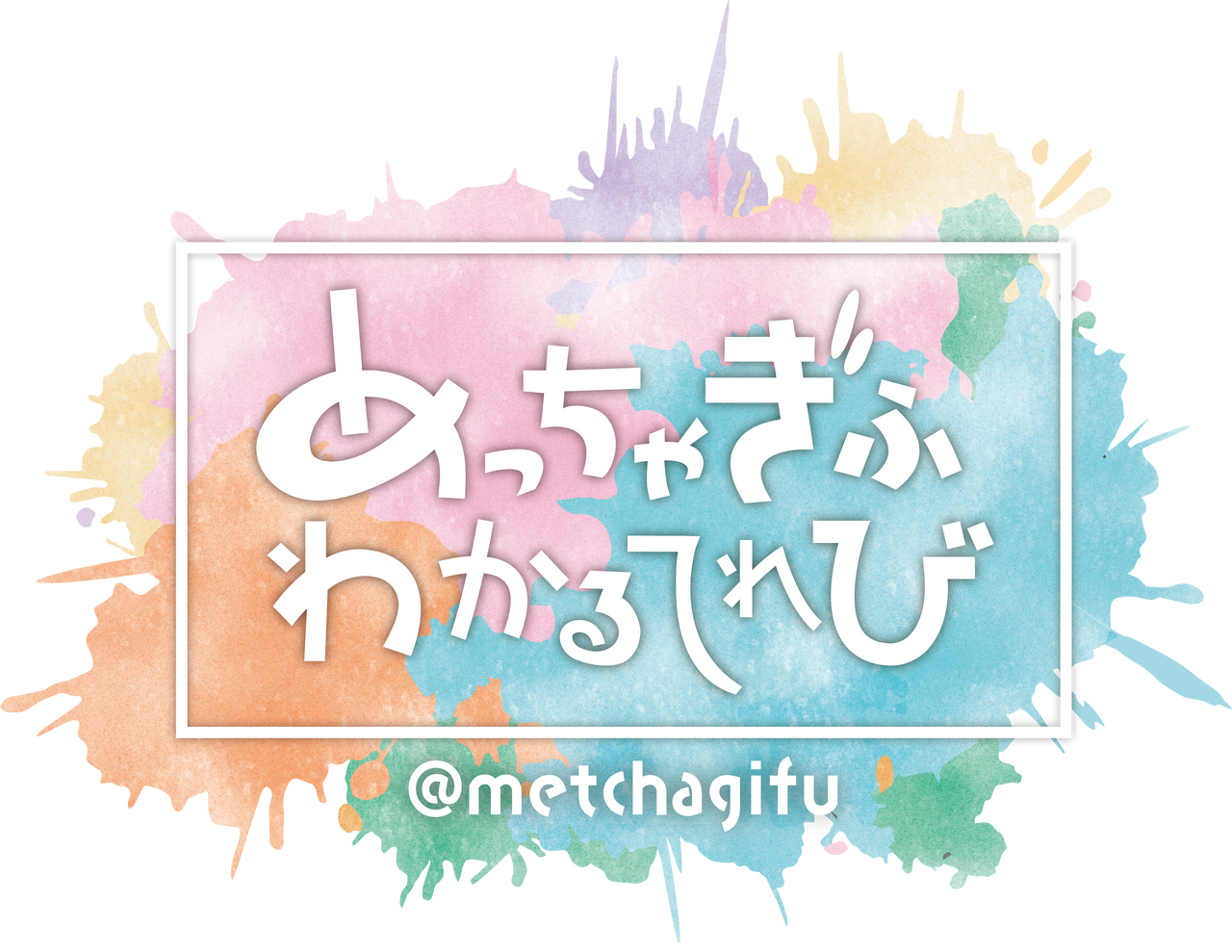テレビ
煌く岐阜

月曜 よる11時3分~11時6分
2025年1月の放送
1月6日(月)【再放送:1月13日】
池ノ上みそぎ祭(岐阜市)
岐阜の師走の風物詩、池ノ上みそぎ祭。
岐阜市の葛懸(かつらがけ)神社では、伝統行事「みそぎ祭」が毎年行われています。
行われる場所は寒風吹きすさぶ長良川。
鉢巻きふんどし姿の男たちが、「ワッショイ、ワッショイ」と威勢のいい掛け声を響かせながら練り歩きます。
多くの観衆が見守る中、勢いよく川へ飛び込むと水しぶきを上げながら身を清め、勇壮な姿を披露しました。一年のけがれを払い、家内安全・地域繁栄を願う「池ノ上みそぎ祭」を紹介します。
1月20日(月)【再放送:1月27日】
塩ぶり市(高山市)
飛騨高山で江戸時代から続く、年の瀬恒例の「塩ぶり市」。
飛騨地域では、大晦日の夜に縁起物として出世魚のブリを食べ、新年を迎える「年取り」の風習が今も受け継がれています。
高山市公設地方卸売市場では、富山県氷見産をはじめとする大型の天然ブリを仕入れ、三枚おろしにして塩漬け加工した塩ぶりが競りにかけられました。
競り人がブリを高々と掲げると、買い手たちは威勢の良い掛け声を響かせながら、次々と競り落としていきました。
今回は飛騨地域の歴史を刻む、年の瀬の風物詩「塩ぶり市」を紹介します。
2025年2月の放送
2月3日(月)【再放送:2月10日】
花奪い祭り(郡上市白鳥町)
1年の幸福を願う者たちが競い合う「花奪い祭り」。
郡上市白鳥町の長滝白山神社では毎年1月6日に、天井に吊るされた縁起物の花笠を奪い合う、花奪い祭りが行われます。
花奪い祭りは、鎌倉時代から続く伝統行事で天井に吊るされた花笠の花を持ち帰ると、家内安全や商売繁盛にご利益があると言われています。
威勢よくスタートした花奪いは、参拝者らが天井から吊り下げられた花笠に向かってやぐらを組み、激しく揺さぶって、奪い合いました。
今回は美濃の春を告げる、伝統と熱気の競演「花奪い祭り」を紹介します。
2月17日(月)【再放送:2月24日】
三寺まいり(飛騨市古川町)
飛騨古川の冬を彩る、伝統と幻想の灯り「三寺まいり」。
飛騨市古川町で200年以上続く伝統行事で、親鸞聖人をしのんで、町内にある三つの寺を参拝します。明治・大正時代には、製糸工場から帰省した若い女性たちが着飾って参拝し、男女の出会いの場「縁結びの行事」としても 知られるようになりました。
瀬戸川沿いには大小さまざまな、千本のろうそくが灯され、幻想的な雰囲気が漂います。
今回は灯りと祈りが織りなす、冬の風物詩「三寺まいり」を紹介します。
2025年3月の放送
3月3日(月)【再放送:3月10日】
今尾の左義長(海津市)
燃え盛る炎に願いを込める、伝統の火祭り「今尾の左義長」。
およそ400年続く伝統行事で、県の重要無形民俗文化財に指定されており、火伏せや無病息災を願い、行われてきました。
しめ縄や旗を飾った竹みこしが順につり込まれ、火がつけられると、一気に火柱が上がります。
派手な化粧と色鮮やかな長襦袢姿の若衆が縄を持ってみこしに巻きながら勢いよく駆けまわり、恵方の方角に引き倒しました。
今回は炎と祈りが織りなす、冬の勇壮な祭典「今尾の左義長」を紹介します。
3月17日(月)【再放送:3月24日・3月31日】
つりびな(大垣市墨俣町)
大垣市墨俣町では、地域の魅力を伝える 「墨俣つりびな小町めぐり」が開催されています。
かつて宿場町として栄えたこの地では、雛祭りの時期に合わせ、町内のいたる所に色鮮やかなつりびなが飾られます。
今年は、およそ800点のつりびなが展示され、地元の職人や住民の手仕事による温かみのある作品が並びます。
「すのまた宿 池田屋脇本陣」では、ひな壇とともに展示されたつりびなが華やかさを添え、訪れる人々を魅了しました。
今回は町全体が優雅な世界に包まれる、美しく繊細な「つりびな」を紹介します。
2025年4月の放送
4月7日(月)【再放送:4月14日】
白線流し(高山市)
高山市三福寺町にある斐太高校では、卒業生が門出を迎えるこの日、80年以上続く伝統行事「白線流し」が行れます。
男子生徒は学生帽に巻いた白線を、女子生徒はセーラー服の白いスカーフを結び、それをクラスごとに一本の白線にして、大八賀川に流します。
卒業生が家族や先生たちに見守られながら、「ありがとう」と感謝の言葉を贈り、白線を川へ託しました。今回は友情の絆を結び、未来へ託す「白線流し」を紹介します。
4月21日(月)【再放送:4月28日】
淡墨桜(本巣市根尾)
本巣市に佇む「淡墨桜」は、高さ17.3m、太さ9.4m。
継体天皇(けいたいてんのう) が植えたと伝えられており、樹齢はなんと1500年以上。
日本三大桜のひとつに数えられ、国の天然記念物に指定されています。
蕾のときは薄いピンク、満開に至っては白色、散りぎわには特異の淡い墨色を帯びてくることから「淡墨桜」と名づけられました。
その神秘的な姿を一目見ようと、多くの観光客が訪れ、桜の下で春の訪れを楽しんでいます。
今回は淡くにじむ花びらに、時代の息吹を映す「淡墨桜」を紹介します。
2025年5月の放送
5月5日(月)【再放送:5月12日】
春の高山祭(高山市)
城下町・飛騨高山に春の訪れを告げる「春の高山祭」。
高山祭は、春の「山王祭」と秋の「八幡祭」からなる伝統行事で、日本三大美祭のひとつにも数えられています。
今年は3年ぶりに、きらびやかな祭屋台12台すべてが勢ぞろい。
金箔や漆、精緻な彫刻が施された豪華絢爛な屋台が蔵から曳き出され、町並みに美しい彩りを添えます。
中でも、およそ140年ぶりに大改修を終えた「恵比寿台」が披露され、からくり屋台の演舞には、観客から大きな拍手が送られました。
今回は春爛漫の高山に、伝統の息吹が舞い降りる「高山祭」を紹介します。
5月19日(月)【再放送:5月26日】
古川祭(飛騨市)
飛騨の春を告げる、勇壮な「古川祭」。
およそ400年の伝統を誇り、国の重要無形民俗文化財にも指定されています。
中でも最大の呼び物が「起し太鼓」。夜のまつり広場に現れるのは、直径80センチの大太鼓を載せたやぐら。さらし姿の男たちが太鼓を打ち鳴らしながら、町を練り歩きます。
道中では、「付け太鼓」を担いだ男たちがやぐらへ突進。もみ合いながらぶつかり合う姿は、まさに春の熱気そのものです。町を揺らす音と、人々の熱情。
今回は、飛騨の魂が今も息づく「古川祭」を紹介します。
2025年6月の放送
6月2日(月)【再放送:6月9日】
ミズバショウとリュウキンカ(飛騨市宮川町)
標高およそ1000メートルにある『池ケ原湿原』には、およそ30万株のミズバショウが自生しています。
池ケ原湿原では、太古より豊かな湧き水が出ていて、その恵みを受けて、ミズバショウが咲き、そのミズバショウを包み込むように黄色の花をつけるリュウキンカが咲き誇ります。
今回は池ケ原湿原のミズバショウとリュウキンカを紹介します。
6月16日(月)【再放送:6月23日・30日】
飛騨位山トレイル(高山市一之宮町)
飛騨位山トレイルは、高山市一之宮町(いちのみやまち)のスキー場を発着点に、標高1529メートルの位山などに挑む、トレイルランの大会です。
全国から集まったランナーが、未舗装のコースに挑みます。
日本二百名山に数えられる位山を駆けぬける「飛騨位山トレイル」を紹介します。
2025年7月の放送
7月7日(月)【再放送:7月14日】
曽根城公園 ハナショウブ(大垣市曽根町)
ハナショウブの名所として知られる、大垣市の曽根城公園。
園内には、約27,000株のハナショウブが植えられています。
白や紫、水色などカラフルな花を楽しみながら、園内を散策することができます。
今回は曽根城公園のハナショウブを紹介します。
7月21日(月)【再放送:7月28日】
犀川堤 アジサイ(大垣市墨俣町)
大垣市墨俣町の犀川堤には、南北およそ1.2キロにわたって、アジサイが植えられています。春は桜のトンネルとしてにぎわう並木道ですが、初夏にはアジサイを楽しむことができます。
今回は幻想的なグラデーションを楽しむことができる、犀川堤のアジサイを紹介します。
2025年8月の放送
8月4日(月)【再放送:8月11日】
養老の滝 滝開き式(養老郡養老町)
滝百選・名水百選に選ばれる、養老郡養老町の「養老の滝」。
養老の滝は落差およそ30メートル、幅およそ4メートルで、滝の水は「老いを養う霊水」として伝わっています。
夏になると、行楽シーズンの到来を告げる「滝開き式」が行われ、安全を祈願します。
今回は夏の訪れを告げる「養老の滝 滝開き式」を紹介します。
8月18日(月)【再放送:8月25日】
白山白川郷ホワイトロード(大野郡白川村)
大野郡白川村と石川県を結ぶ山岳有料道路「白山白川郷ホワイトロード」。
この道路は、白山国立公園の中を走る全長33.3キロの有料道路で、雪のため冬は閉鎖されます。今年は7月11日に全線開通となりました。
今回は、限られた期間しか見ることが出来ない大自然を楽しめる、「白山白川郷ホワイトロード」を紹介します。
2025年9月の放送
9月1日(月)【再放送:9月8日】
ぎふ長良川花火大会(岐阜市)
岐阜市 長良川河畔で行われる「ぎふ長良川花火大会」。
清流長良川と金華山。
豊かな自然を背景に繰り広げられる打ち上げ幅600メートルの「超ウルトラワイドスターマイン」が見どころ。
今回は、「ぎふ長良川花火大会」を紹介します。
9月15日(月)【再放送:9月22日・9月29日】
郡上おどり(郡上市八幡町)
2022年にユネスコ無形文化遺産に登録された郡上おどり。
400年余りの伝統を誇ります。
夜通し踊る「徹夜踊り」は、毎年お盆に4夜連続で行われます。
おはやしを奏でる屋形(やかた)を中心に、全国から訪れたおよそ6万人の踊り手が、幾重にも輪を広げながら続々と踊りに参加します。
今回は、「郡上おどり」を紹介します。
2025年10月の放送
10月6日(月)【再放送:10月13日】
車田の稲刈り(高山市松之木町)
岐阜県の重要無形民俗文化財に指定される高山市松之木町(まつのき・まち)の「車田(くるまだ)」。
三重県の伊勢神宮に奉納する米を栽培していたと伝えられる丸い田んぼで、古くから伝わるのは高山市と新潟県佐渡市の2か所のみとされています。
今回は、高山市の「車田の稲刈り」を紹介します。
10月20日(月)【再放送:10月27日】
岐阜城パノラマ夜景(岐阜市)
2025年9月に「日本夜景遺産」に認定された「岐阜城パノラマ夜景」。
岐阜市の金華山山頂の岐阜城から濃尾平野の夜景を楽しむことができます。
「岐阜城パノラマ夜景」は、ゴールデンウイークや夏休み、秋の休日など、1年の一定期間に岐阜城天守閣の営業時間を延長して行われています。
今回は、「岐阜城パノラマ夜景」を紹介します。
2025年11月の放送
11月3日(月)【再放送:11月10日】
秋の高山祭 宵祭(高山市)
10月9日の夕方から開催される、秋の高山祭の「宵祭」。
高山祭は2016年にユネスコ=国連教育科学文化機関の無形文化遺産に登録された「山・鉾・屋台行事」の1つで、秋の祭は「櫻山八幡宮」の例祭です。
笛や太鼓による祭りばやしが響く中、ちょうちんを灯した祭屋台がゆっくりと古い街並みを巡り、幻想的な雰囲気に包まれます。
今回は、「秋の高山祭り 宵祭」を紹介します。
11月17日(月)【再放送:11月24日】
屋根のふき替え 白川村の合掌造り(大野郡白川村)
住民同士が助け合う白川村伝統の「結」による、かやぶき屋根をふき替える作業。
屋根のふき替えは、およそ30年に1度。
今回は、「白川村の合掌造り 屋根のふき替え」を紹介します。
2025年12月の放送
12月1日(月)【再放送:12月8日】
大矢田神社もみじ谷(美濃市)
大矢田(おやだ)神社もみじ谷。神社一帯のヤマモミジ樹林は国の天然記念物に指定されていて、飛騨・美濃紅葉三十三選に数えられています。
赤や黄色に染まるおよそ3000本のモミジが多くの人を楽しませます。
今回は、大矢田神社もみじ谷をご紹介します。
12月15日(月)【再放送:12月22日・12月29日】
木曽三川公園センター イルミネーション(海津市)
海津市の木曽三川公園センターの冬を彩る、「イルミネーション」。
普段は花や緑が広がる園内。この期間は、50万球を超えるLEDによってカラフルな光に包まれます。
番組概要
「ふるさと・岐阜の自然・町並み・伝統行事」など、岐阜の魅力を余すことなく盛り込み、ふるさとの良さを後世に伝え守っていく…そんな様々な“岐阜の煌き(きらめき)”たちを紹介します。