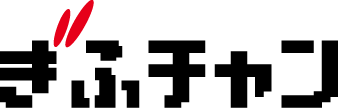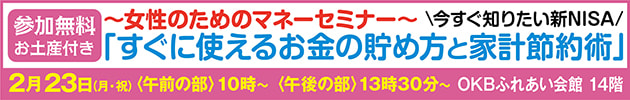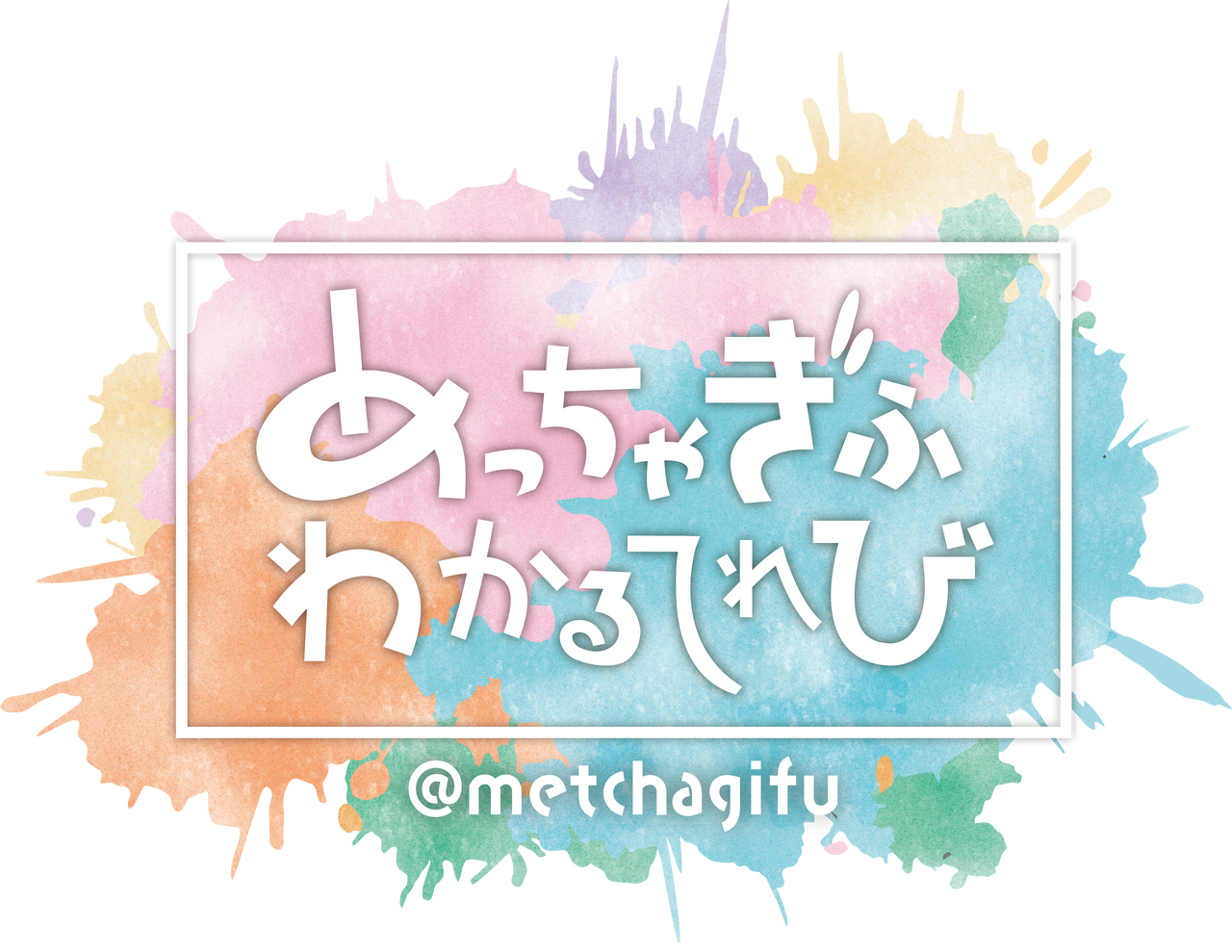テレビ
煌く岐阜

月曜 よる11時3分~11時6分
2023年1月の放送
1月2日(月)
一位一刀彫(高山市)
一位一刀彫は「イチイ」という飛騨の木を生かし、彫刻刀で彫り上げる国の伝統工芸品です。高山市本町で行われる、一位一刀彫をご紹介します。
(再放送:1月9日)
1月16日(月)
三輪神社(揖斐川町)
三輪神社は「大黒様」で親しまれる大国主大神が祭られ昔から親しまれている由緒ある神社です。揖斐川町の三輪神社をご紹介します。
(再放送:1月23日・1月30日)
2023年2月の放送
2月6日(月)
元服式(本巣市)
元服式は揖斐郡揖斐川町の徳山ダムの建設で廃村となった旧徳山村に伝わる儀式です。
本巣市の徳山神社で行われた元服式をご紹介します。
(再放送:2月13日)
2月20日(月)
寒ざらしそば(高山市)
寒ざらしそばは冷たい川の水に浸し甘みを引き出す伝統行事です。
高山市の寒ざらしそばをご紹介します。
(再放送:2月27日)
2023年3月の放送
3月6日(月)
梅(岐阜市)
冬空にほころぶ、梅。
梅の名所、岐阜市の梅林公園ではこの時期色とりどり梅の花が見ごろを迎えます。
梅林公園にはおよそ50種、1300本の梅が植えられており、早咲きから中咲き、遅咲きと様々な梅を楽しむことができます。花言葉は「高潔」。寒風が吹く中、凛と咲きほこる梅の姿が春の訪れを感じさせます。ほのかに香る春、梅を紹介します。
(再放送:3月13日)
3月20日(月)
セリバオウレン(高山市)
春の訪れを告げる、セリバオウレン。
高山市中心部にある城山(しろやま)公園の山肌にはセリバオウレンがほころび、白い花が顔をのぞかせています。キンポウゲ科の多年草で高さが10センチほどの茎の先に1センチにも満たない可憐な花を咲かせます。「春の妖精」とも呼ばれ、雪解けと共に咲き、春の訪れ感じさせます。小さく可憐な春の息吹、セリバオウレンを紹介します。
(再放送:3月27日)
2023年4月の放送
4月3日(月)
春の高山祭 のぼり旗(高山市)
春の高山祭の開催を知らせるのぼり旗。
豪華絢爛な祭り屋台やからくり奉納で知られる高山祭。その開催に伴い、地元の建築業者がのぼり旗を付けた高さ15メートルの支柱をクレーンでつり上げて設置しました。
のぼり旗と提灯がお目見えするのは4年ぶりです。のぼり旗は縦およそ10メートル、幅およそ1メートルの大きさで「飛騨高山祭」の文字が染め抜かれています。
見る人の心を踊らせるのぼり旗を紹介します。
(再放送:4月10日)
4月17日(月)
飛騨生きびな祭(高山市)
飛騨路を彩る、飛騨生きびな祭。
養蚕や農業の繫栄と女性の幸福を願う祭で、今年で70回を数えます。
春の訪れが遅い飛騨地方のひな祭りは1カ月遅れ。
地元の女性9人が内裏や后などの雛人形に扮してまちを練り歩きます。
青空と咲き誇る桜のもと繰り広げられる、平安絵巻。雅な和の世界へと誘います。
女性たちの晴れの舞台、飛騨生きびな祭を紹介します。
(再放送:4月24日)
2023年5月の放送
5月1日(月)
ヒトツバタゴ(岐阜市金町)
初夏の風物詩、ヒトツバタゴ。
岐阜市金神社のヒトツバタゴが見ごろを迎えました。
モクセイ科の落葉樹林で緑の葉にまるで雪が積もったように、白い花を咲かせます。
その姿から呼ばれる愛称は「ナンジャモンジャ」。
初夏に降り積もる綿雪(わたゆき)が訪れる人を楽しませます。
季節外れの雪景色、ヒトツバタゴを紹介します。
(再放送:5月8日)
5月15日(月)
春の高山祭(高山市)
飛騨路を彩る、春の高山祭。
秋の祭りとともに、日本三大美祭の1つに数えられる春の高山祭。日枝神社の例祭で、江戸時代から続く伝統の行事です。夜には提灯を灯した11の屋台が、氏子に曳かれて中心市街地を練り、町並みをあたたかな光に包みます。
夜祭が行われるのは6年ぶり。
国内外の観光客が久方の幻想的な光に酔いしれます。豪華絢爛な屋台が輝く春の高山祭を紹介します。
(再放送:5月22日・5月29日)
2023年6月の放送
6月5日(月)
野麦峠まつり(高山市)
着物に草履履きの行列が山行する、野麦峠。
明治から昭和初期にかけて寒さの厳しい冬の時期に飛騨地方の若い工女たちが、長野県の製糸工場へ出稼ぎに向かった道。その足跡を伝えようと、当時の姿に扮した地元の女性たち15人が、およそ1キロにわたる新緑の古道を歩きます。
峠にある「乙女地蔵尊」に手を合わせ、当時の工女たちの労苦を偲びます。
工女たちへの感謝を伝承する、野麦峠まつりを紹介します。
(再放送:6月12日)
6月19日(月)
白川郷田植え祭り(大野郡白川村)
里山に田植え唄が響く、白川郷田植え祭り。
合掌造りの家屋を背景に早乙女姿の女性が稲の苗を手植えします。
昔ながらの田植えの風景を残そうと企画され、今年で38回目を数えます。
コロナ禍や雨の影響により開催されるのは4年ぶり。横一列に並んだ早乙女たちは田植え唄に合わせ苗を手植えし、観光客はその様子を思い思いにカメラに収めます。
昔ながらの里山の風景が広がる、白川郷田植え祭りを紹介します。
(再放送:6月26日)
2023年7月の放送
7月3日(月)
飛騨牛の放牧(高山市荘川町)
飛騨の里山で行われる、飛騨牛の放牧。
荘川町の牧場にやってきたのは、おなかに子どもがいる雌牛たち。
母牛が新鮮な牧草を食べ、適度な運動をすることで、元気な子牛を生むようにと、毎年放牧が行われています。冬の間、牛舎で過ごした牛たちは、広々とした牧場で元気に走り回ります。
飛騨の夏の風物詩、飛騨牛の放牧を紹介します。
(再放送:7月10日)
7月17日(月)
長良川鵜飼(岐阜市)
岐阜の夏の風物詩、長良川鵜飼。
暗闇に浮かぶ篝火が水面を照らし、伝統装束に身を包んだ鵜匠が、鵜を見事な手縄さばきで操ります。鵜匠と鵜が一体となって繰り広げる、伝統漁法「鵜飼」。1300年以上受け継がれた美技が、タイムスリップしたような幽玄の世界へと誘います。
清流の照らす伝統の技、長良川鵜飼を紹介します。
(再放送:7月24日・31日)
2023年8月の放送
8月7日(月)
飛騨メロン(高山市)
飛騨高山の夏の特産品、飛騨メロン。
高山市丹生川町の農家ではこの時期、収穫の最盛期を迎えます。
盆地特有の朝晩と日中の寒暖差が生み出す、コクのある甘さとみずみずしい果肉。
糖度14を超える大玉メロンが次々と収獲されていきます。
飛騨高山の地がもたらす甘美な果実、飛騨メロンを紹介します。
(再放送:8月14日)
8月21日(月)
ぎふ長良川花火大会(岐阜市)
ぎふの夏の風物詩、ぎふ長良川花火大会。
次々と打ちあがる花火が夜空を鮮やかに染め上げます。
およそ600メートルの「超ウルトラワイドスターマイン」、清流長良川を表現した淡い水色の花火など大会テーマとなった平和に願いを込めたおよそ1万発の花火が打ち上がりました。
4年ぶりに岐阜の夜空を彩った大輪の花に浴衣姿の人や家族連れらからは盛んに拍手が送られました。岐阜の夜空を彩る大輪、ぎふ長良川花火大会を紹介します。
(再放送:8月28日)
2023年9月の放送
9月4日(月)
天空の茶畑(揖斐川町)
一面に茶畑が広がる、揖斐川町春日上ヶ流(かすがかみがれ)地区。
朝晩と日中の寒暖差が激しい気候がお茶づくりに適していることから、山肌を添うように茶畑が開拓されました。標高300mほどの山の中腹に茶畑が一面に広がるその景色が、南米ペルーの世界遺産「マチュピチュ」に似ていることから、「天空の茶畑」「岐阜のマチュピチュ」と言われています。長い年月をかけて紡がれた絶景。
春日上ヶ流地区の歴史を伝える、天空の茶畑を紹介します。
(再放送:9月11日)
9月18日(月)
地歌舞伎(岐阜市)
全国各地に広がった歌舞伎が一般庶民により芝居小屋や神社の祭礼で演じられ、楽しまれてきた「地歌舞伎」。
役者と観客が一体となって舞台を盛り上げるのがその醍醐味。演目中に役者が見栄を切った瞬間に声掛けする「大向こう」や紙に小銭を包んで客席から投げ入れる「おひねり」で観客も参加。会場が一体となってつくりあげる演劇は多くの人々を魅了し、地域に根ずく伝統文化となっています。観るだけではなく、自ら演じるようになった伝統芸能「地歌舞伎」を紹介します。
(再放送:9月25日)
2023年10月の放送
10月2日(月)
飛騨の赤山椒(高山市)
真っ赤に色づいた山椒の実の収穫が最盛期を迎える高山市奥飛騨温泉郷。
秋の訪れとともに赤く完熟した山椒は「赤山椒(あかさんしょう)」と呼ばれ、甘い上品な香りとマイルドな辛みが特徴です。
鮮やかに赤く色づいた実を手作業で次々と摘み取ると、辺りには芳醇な香りが広がります。鮮やかな赤で、香りで、秋の足音を知らせる赤山椒を紹介します。
(再放送:10月9日)
10月16日(月)
きつね火まつり(飛騨市)
飛騨市に伝わる民話「きつねの嫁入り」をモチーフに、1990年から町おこしの一環として続いてきた飛騨市の秋の恒例イベント「きつね火(び)まつり」。
白いひげや赤い鼻などキツネ顔にメークした花嫁と花婿が人力車に乗り飛騨古川を行列とともに練り歩きます。
そんな、古い町並みを松明の灯りが照らす「きつね火まつり」を紹介します。
(再放送:10月23日・30日)
2023年11月の放送
11月6日(月)
全国和紙画展(美濃市)
美濃市の特産、和紙で描く絵画の公募展「全国和紙画展」。
和紙を普及させその芸術的価値を高めようと、毎年開催されています。
絵の題材に合わせて切る、ちぎる、よじる、しわをつけるといった和紙ならではの加工が施され、来場者の目を引きます。
そんな、和紙のさまざまな表情が見える「全国和紙画展」を紹介します。
(再放送:11月13日)
11月20日(月)
ぎふ信長まつり(岐阜市)
今回は岐阜ゆかりの戦国武将・織田信長をたたえる「ぎふ信長まつり」をご紹介します。
金華橋通りを彩るのは、地元の高校生らによるパレード。
火縄銃鉄砲隊の模擬射撃に続く騎馬武者行列には公募で選ばれた市民が信長や濃姫に扮し、馬や輿(こし)に乗って登場。訪れた大勢の人々を沸かせました。
華やかに繰り広げられる時代絵巻をお楽しみください。
(再放送:11月27日)
2023年12月の放送
12月4日(月)
伊自良大実連柿(山県市)
今回は山県市の家の軒先を彩る「伊自良大実連柿(いじらおおみれんがき)」をご紹介します。
皮をむいた柿を3個ずつ串に通してひもで一連にし、20日間ほど干して作られる干し柿。こうすることで甘味が凝縮されます。
山県市の特産である「伊自良大実柿」は干し柿にすると糖度は60度以上になるといい、“福をかき集める”正月の縁起物とも言われています。
木枯らしが揺らすオレンジ色のカーテンをお楽しみください。
(再放送:12月11日)
12月18日(月)
菜洗い(高山市)
今回は高山市の晩秋の風物詩、漬物づくりの「菜洗い」をご紹介します。
水温およそ6度の小川でタワシを使って白菜や大根、赤カブを丁寧に水洗いします。
飛騨地方の冬の保存食として欠かせない漬物。
そんな漬物を作る工程のひとつ「菜洗い」は、かつては飛騨地方の各地で見られました。飛騨地方の越冬の準備の様子をお楽しみください。
(再放送:12月25日)
番組概要
「ふるさと・岐阜の自然・町並み・伝統行事」など、岐阜の魅力を余すことなく盛り込み、ふるさとの良さを後世に伝え守っていく…そんな様々な“岐阜の煌き(きらめき)”たちを紹介します。